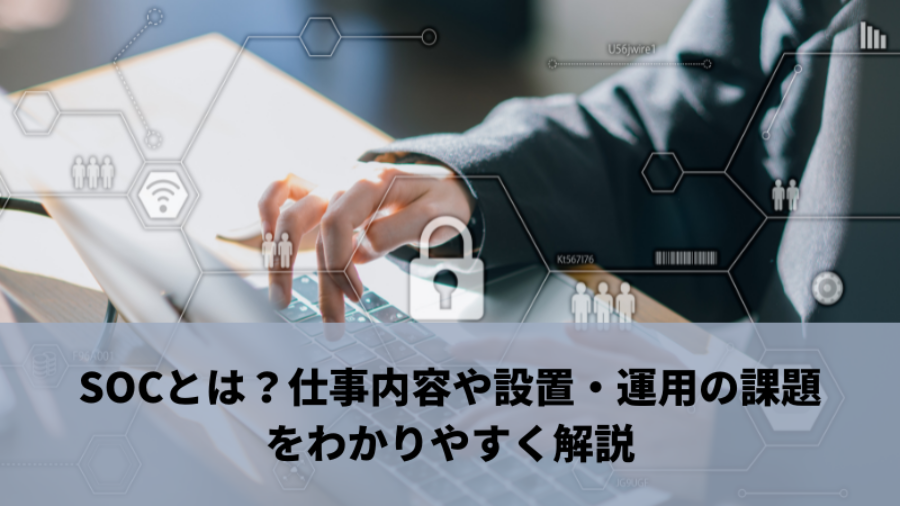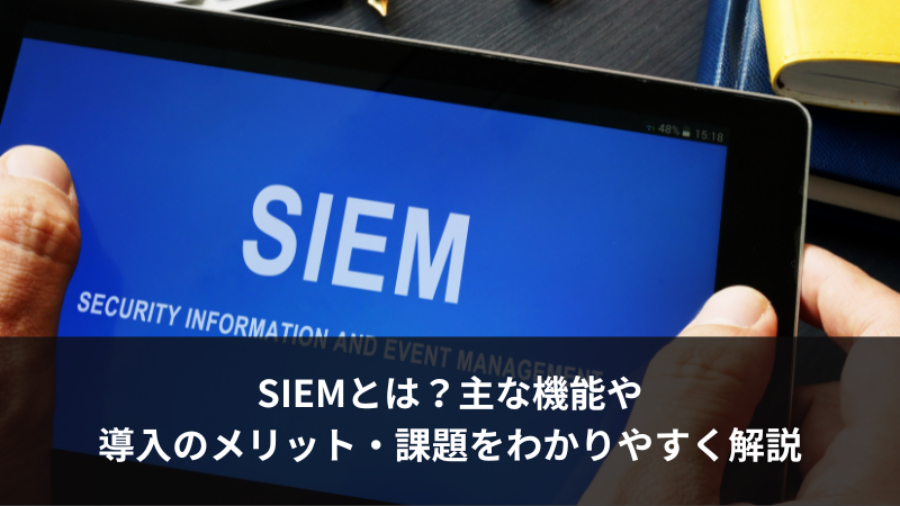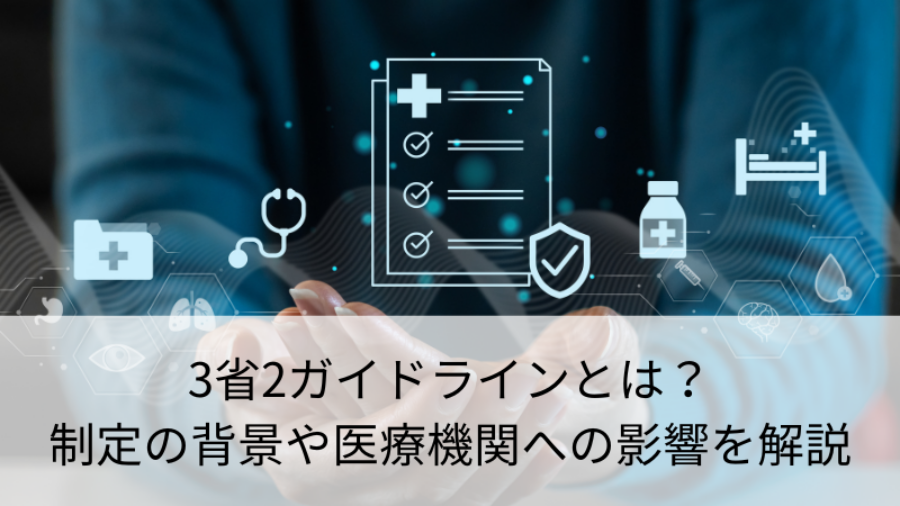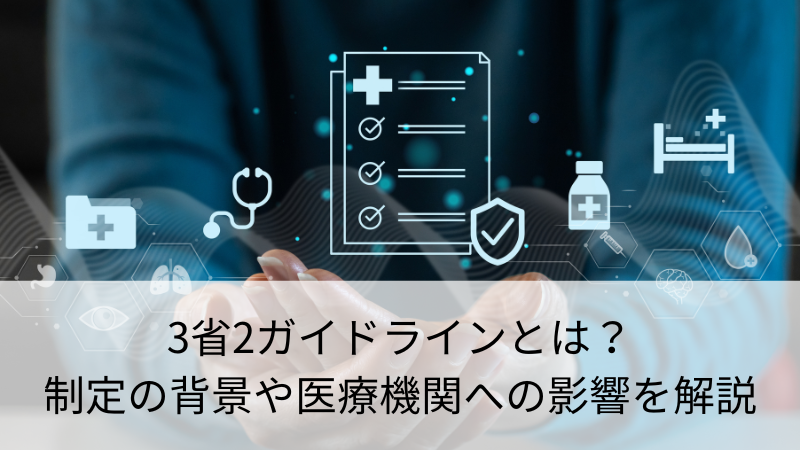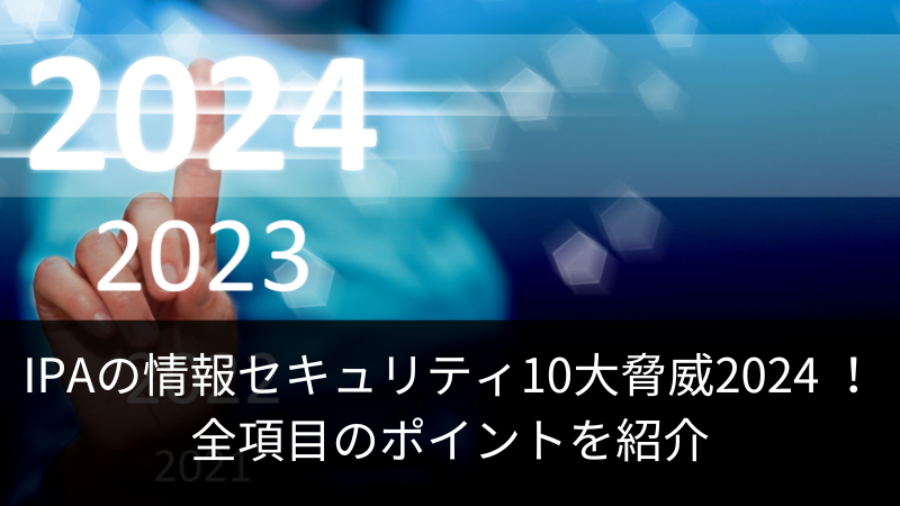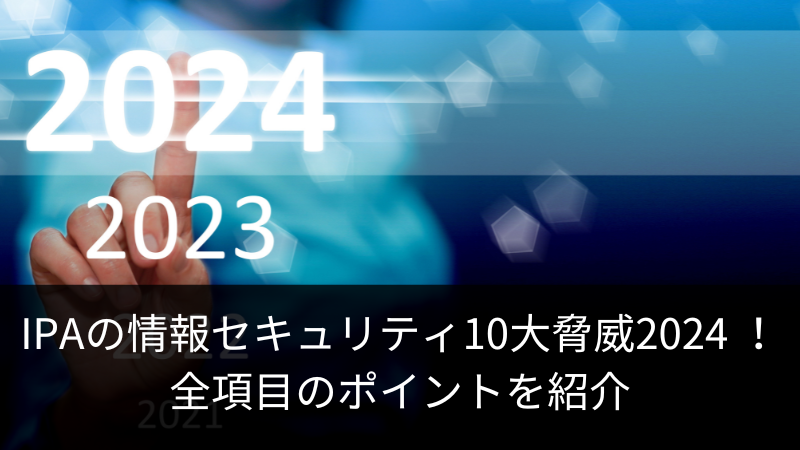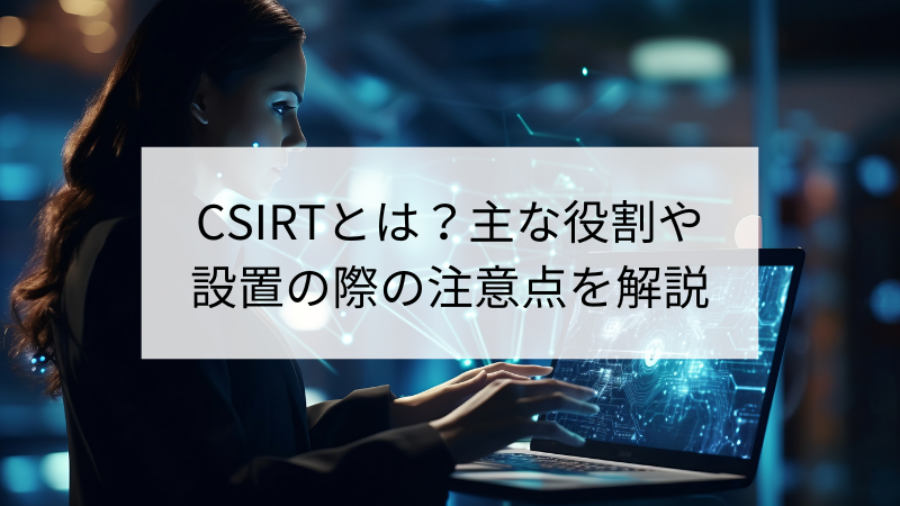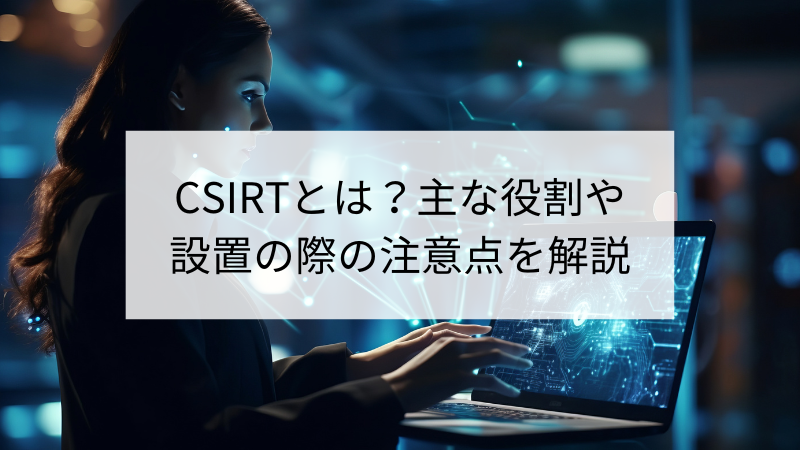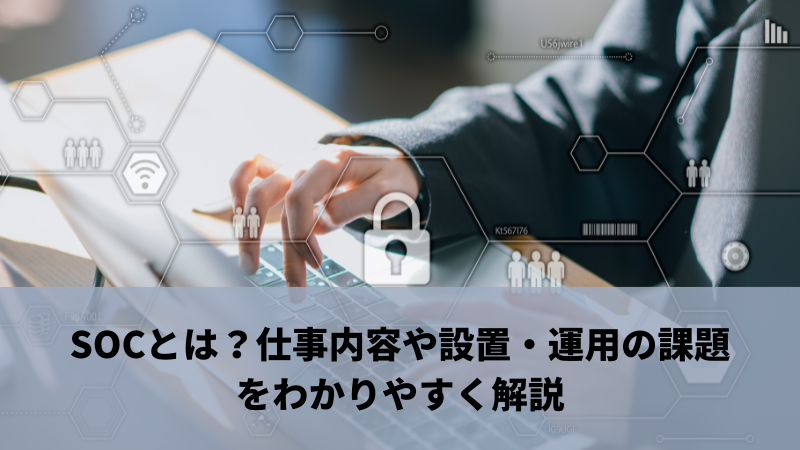
現代のデジタル環境において、企業のセキュリティ対策としてSOC(Security Operation Center)は重要な役割を果たしています。本記事ではSOCの重要性やその背景、CSIRTやMDRとの違いを解説します。また、自社でSOCを導入する際に直面する課題と、SOCなしでのセキュリティ対策としてWAFサービスについても触れます。
SOC(Security Operation Center)とは
SOC(ソック)とは、24時間365日体制でネットワークやシステムを監視し、サイバー攻撃の検知や対応を行う専門組織・チームのことです。不正アクセスやサイバー攻撃、マルウェア感染などのセキュリティインシデントを予防し、それらが発生した場合には迅速かつ効果的に対処するための組織として機能します。
・CSIRTやMDRとの違いは?
CSIRT(Computer Security Incident Response Team:シーサート)は、セキュリティインシデントが発生した際に復旧活動やリスク評価、関係各所への連絡を行う組織です。SOCはインシデント発生前の予防を担当し、CSIRTは発生後の対処を担当します。
MDR(Managed Detection and Response:エムディーアール)は、SOCが行う監視や検知、CSIRTが行う対処などの役割を外部のサービスプロバイダーに委託できるサービスです。自社の専門的なリソースが不足している場合などに活用されています。
SOCが重視される背景
近年、IoTやDXの推進に伴い、データの生成と利用が急増しています。また、クラウドサービスやリモートワークが普及したことで、多様なデバイスや場所から企業の情報にアクセスするケースが増加しました。こうした中で、より高度化・巧妙化したサイバー攻撃が増えており、企業と従業員個人のセキュリティリスクは高まるばかりです。そのため企業はサイバー脅威に対する防御力を強化するとともに、セキュリティインシデントへ迅速に対応することが極めて重要な課題となっています。
このような背景から、インシデントを早期に検知し、迅速な対応を行うSOCが求められています。
SOCの主な仕事内容
インシデントの早期発見と迅速な対応を行うために、SOCは高度な専門性をもとに以下のような仕事に従事しています。
・ネットワーク・システム・デバイスの監視
ネットワークやアプリケーションなどを24時間365日体制で監視します。これには、ネットワークトラフィックのモニタリング、不正アクセスの検出、システムの異常な動作の監視などが含まれます。また、監視ツールやシステムログを活用することで、正常な動作から外れたアクティビティを検知し、潜在的なインシデントを特定して被害を事前に防ぎます。
・インシデントの検知とアラート発信
ネットワークやシステム上で異常なアクティビティを検知すると、ただちにSOCにアラートが発信されます。SOCはインシデントの発生時刻や種類、重要度、影響範囲、対処方法などの情報を調査するとともに、必要に応じて関係者への通知・連絡を行います。CSIRTなどほかのセキュリティチームとも連携し、被害を最小限に抑えるための適切な措置を講じるのも重要な仕事です。
・セキュリティ対応策の立案とアドバイス
インシデントが検出されると、SOCは詳細な分析を行い、攻撃の原因や影響を把握します。次に、分析結果をもとに対策を立案し、ソフトウェアの脆弱性の修正やセキュリティポリシーの強化などの措置を検討します。さらに、関係各所に対してセキュリティに関するアドバイスを提供し、将来への備えを支援します。
自社でSOCの設置・運用をする場合の課題
セキュリティ対策としてSOCを導入する場合、自社で構築するか外部に委託するかを選択することになります。ただし、自社で設置・運用する場合には、以下の事項に留意する必要があります。
・人材の確保が必要
SOCの運用には、セキュリティエンジニアやアナリストなどの専門的な人材が必要です。サイバー攻撃は国内・国外から昼夜関係なく実行されるため、24時間365日の体制で監視や対応を行う必要があり、二交代制や三交代制で監視するための交代要員も欠かせません。
しかし、総務省の「令和2年 情報通信白書」によれば、日本はアメリカやシンガポールと比較して、専門的なセキュリティ人材の充足状況にほとんど満足していないことがわかります。
参照元:総務省|令和2年 情報通信白書
セキュリティ人材が不足している理由としては、専門的な人材の教育・訓練に多大な時間やコストがかかることや、市場の競争激化、採用コストの上昇などが挙げられます。
・ログ分析の処理量が増大すると分析が難しくなる
大量のインターネットデータのやり取りに伴い、ログ分析の処理量も増大し、分析が困難になることがあります。この増大する処理量に対処するためには、いくつかの課題が生じます。まず、処理時間が増加し、リアルタイムな分析が困難になります。また、データの増加により可視性が低下し、異常の検出や対応に遅れが生じる可能性があります。さらに、誤検知や過検知のリスクが増え、アナリストたちの負担が増大します。
こうした課題に対処するためには適切なツールやリソースの確保が必要ですが、自社でSOCを構築する場合には多大なコストがかかります。
SOCなしでセキュリティを強化する方法
自社でSOCの構築が困難な場合、WAFサービスの導入を検討することもひとつの方法です。WAFはWebアプリケーションレベルでのセキュリティを強化するためのサービスです。クロスサイトスクリプティングやSQLインジェクションなど、従来のネットワークセキュリティ製品では防ぎきれないサイバー攻撃を防止できます。リアルタイムでトラフィックを監視し、不正なアクセスや攻撃パターンを検知します。
特にクラウド型WAFサービス「Cloudbric WAF+」は、直感的なインターフェースで誰でも使いやすく、専門的な人材が不在でも簡単に導入・運用できるため、おすすめです。
このサービスはSOCの機能も含んでおり、インシデントの詳細な分析や迅速な対応を行い、自動でレポートを作成します。さらに、シグネチャー基盤検知方式でインシデントを検知する従来のWAFとは異なり、ロジックベースの方式を採用して効果を高めています。
まとめ
SOCは24時間365日体制でネットワークやシステムを監視し、インシデントを予防・対処します。IoTやDXの進展、リモートワークの普及などに伴い、セキュリティリスクが増加し、SOCの重要性が高まっています。ただし、人材確保の難しさやログ分析処理量の増大などの課題があり、自社での構築は困難な場合もあります。そのようなときには、クラウド型WAFサービスの「Cloudbric WAF+」を利用することを推奨します。
▼WAFをはじめとする多彩な機能がひとつに。企業向けWebセキュリティ対策なら「Cloudbirc WAF+」
▼製品・サービスに関するお問い合わせはこちら